「カーボン・デモクラシー」 エネルギー供給体制が民主主義の姿を決める
「カーボン・デモクラシー」 エネルギー供給体制が民主主義の姿を決める

19世紀末から20世紀前半にかけて世界各地で民主主義が著しく進展し、大衆が政治に参加するようになりました。この大躍進の原動力については、社会の進歩や政治意識の向上などによって説明するのが普通でした。でも、じつはもっと物質的なところに原因があるのかもしれない。すなわち生産と労働のシステムの変化によるところが大きく、具体的には石炭の普及が大衆民主主義を可能にし、石油がそれを弱体化させた。こういう面白いテーゼを打ち出しているのが、コロンビア大学の中東・アフリカ研究者のティモシー・ミッチェル教授です。ポストコロニアル系の中東歴史家の目から見れば、石油ガス・パイプラインが民主主義を阻害する道具に見えるのは、ある意味あたりまえかもしれません。でもミッチェル教授が言わんとするのは、石油や天然ガスの資源を持つ国々の独裁政権のことだけでなく、それを消費する欧米や日本のような国々の側の民主主義も含めた話なのです。端的に言って、石油経済への切替と巨大パイプライン事業は、20世紀前半に大躍進をとげた大衆民主主義を弱体化させるための道具だったという、たいへん魅力的な主張です。
YouTubeの参考動画 "Carbon Democracy" Timothy Mitchell, Columbia University"
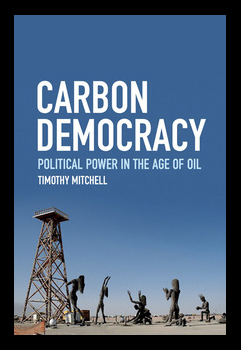 話はまず、石炭の時代にさかのぼります。石炭が基幹エネルギーになった時代に、労働者は強い力を持ち政治的な発言力を持ちました。なぜかというと、生産システムの首根っこを押さえたからです。石炭より前のエネルギー源(薪や動物や人間の労働力)は自然条件に左右されがちで、移動に適さず、基本的に現地消費される拡散した存在でした。これに対し大量生産と移動が可能な石炭は、安定した大量のエネルギー供給を可能にし、国の生産力を飛躍的に増大させました。それと同時に、生産や輸送のために大勢の労働者が一カ所に集中することは組織化を容易にし、彼らが政治・経済的な要求を突きつけることを可能にしました。彼らの武器は、この経済の大動脈を揺るがすストライキです。
話はまず、石炭の時代にさかのぼります。石炭が基幹エネルギーになった時代に、労働者は強い力を持ち政治的な発言力を持ちました。なぜかというと、生産システムの首根っこを押さえたからです。石炭より前のエネルギー源(薪や動物や人間の労働力)は自然条件に左右されがちで、移動に適さず、基本的に現地消費される拡散した存在でした。これに対し大量生産と移動が可能な石炭は、安定した大量のエネルギー供給を可能にし、国の生産力を飛躍的に増大させました。それと同時に、生産や輸送のために大勢の労働者が一カ所に集中することは組織化を容易にし、彼らが政治・経済的な要求を突きつけることを可能にしました。彼らの武器は、この経済の大動脈を揺るがすストライキです。
英国では第一次世界大戦の前夜に炭鉱労働者と港湾労働者たちが組んで、史上初のゼネストを行い支配層を震撼させました。当時の内務大臣ウィンストン・チャーチルは新しい政治勢力の出現に震え上がり、法律を無視して軍隊まで差し向けたそうですが、それでも手も足もでなかった。チャーチルはこれ以降、社会主義を敵視するようになります。その後の数十年間は、国のエネルギー供給システム=生産能力を人質にとった組織労働者が破竹の勢いで改革を迫り、労働者の権利を飛躍的に向上させ、民主主義を大きく前進させました。労働条件の改善、職場の安全性の確保、社会保障制度の充実などの重要な成果も、この時代に達成されました。
これに対する支配層の巻き返しの道具に使われたのが石油でした。石油は労働者に生産システムを脅かすような力を与えません。彼らは分断され、監視されています。石油産業の発展は、最初から労働運動をけん制する意図をもっていたと、ミッチェル教授は言います。たとえば、1914年にシェル石油がベネズエラで石油事業を開始したときのこと。当時のベネズエラの独裁者ゴメス将軍は、自国の石油採掘には同意しましたが精製過程は、オフショアのオランダ領の島(キュラソー島)で行うように要請しました。石油収入は欲しいが、労働者を集中させて政治力を持たせるのは嫌だった。そこで労賃や待遇改善など面倒な要求が起きる工程は外国に移し、産油国政府は石油採掘の手数料や販売価格だけを外国企業と密室で決めるという工夫をしたのです。自国の労働者には関与させない仕組みですから、石油収入についての詳細な報告もありません。こうして政府は国民に報告しなくてすむ巨額の収入を持つようになり、他によい使い道もないことから結局は欧米から武器を購入したりします。うーむ、したたかですね。
このようなオフショア化の狙いは消費地と生産地を切り離し、労働者の統一闘争ができなくするところです。消費地でも石油はタンカーで沿岸の工業地帯に運び込まれ、輸送にかかわる人手がかかりません。しかもタンカーですから、輸入先は臨機応変に切り替えることができます。こうして石油社会になると労働者の闘争能力は激減するのです。こうしてみると、なんだかグローバル化の先取りのような計算ですね。ミッチェル教授は、1980年代の米国の産業空洞化と同じことが、すでに40~50年代にヨーロッパで始まっていたと指摘します。
第二次大戦後のヨーロッパで、「反民主的」な石油エネルギーへの転換を積極的に推進したのは米国です。戦後の復興を支援したマーシャルプランには石油への切り替えが盛り込まれておりました。目的はもちろん、労働運動の力をそぐことです。なにしろ戦後のヨーロッパは民主化の要求が非常に強く、支配層は全力で左翼の鎮圧にかかりました。左翼の牙城だった炭鉱労働組合はとりわけ目障りだったようです。だから強引に石炭生産をやめさせ、労働運動をくじきたかった。ソ連が東欧諸国に供給するシベリア産石油のパイプラインの敷設に対抗して、中東の石油を欧州に運ぶパイプラインの建設ががむしゃらに進められました。最初から政治的な意図で進められてきた石油パイプライン建設ですから、個々のプロジェクトの収益性よりも政治的配慮が優先します。そんなものに民間企業が手を出すのは手厚い政府の保証があるからです。多額の政府資金が民間石油プロジェクトにただ同然で貸し出され、国民にはきちんとした説明などなされません。国際コンソーシアムが組まれ、国民による監視がとどかない中で、巨額の税金がギャンブルに使われているようなものです。
そうして出来上がった現在の石油による非民主的なシステムですが、化石燃料は資源の枯渇という点でも、気候変動が進むという点でも、もう限界を迎えています。再生可能な地域分散型のエネルギー生産への転換が不可避になってきている中で、エネルギーと民主主義の関係に思いをめぐらせることは、次世代のエネルギー源についての議論をずっと面白いものにするでしょう。
今週アップした動画(パイプラインの政治学 「オイルロード」と民主主義)でも、ミッチェル教授がカーボン・デモクラシーについて語っています(だいたい開始から16分ぐらいのところから)
ミッチェル先生はエジプトにも詳しく、現在のエジプトの情勢についても話しています(22分ぐらいから)
日本では『エジプトを再植民地化する』がすでに翻訳されているようですが、Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil (『カーボン・デモクラシー 石油の時代の政治権力』)も大変に面白い本なので、ぜひ翻訳してほしいものです。
さて動画の最初の部分で詳しく語られているパイプラインをめぐる国際政治も、現在のウクライナ情勢などからすると興味深いものがあります。ウクライナをめぐる緊張のたかまりは、今回はプーチン大統領の完勝に終わったようで、西側がどれだけ経済制裁を叫んでも負け犬の遠吠えにしか聞こえません。なんたって燃料供給を握られているのですから、はじめから勝負になりません。でも今回の事件で当然、西側諸国にとってのコーカサスのパイプライン建設(石油もガスも)にいっそうの弾みがつくでしょう。
今後コーカサスが対立の火種になる可能性も大きくなったようなので、こちらも必見といったところでしょうか。番組を見てアゼルバイジャンの石油と天然ガスのパイプラインについて興味が沸いたかたは、もっと詳細な説明がここに載っています(頓挫したナブッコ計画が中心ですが、全般的な状況が図表で分かりやすく書かれています)
http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/5/5226/201403_019a.pdf (特に第5章)
(中野真紀子)
字幕付き動画:パイプラインの政治学 「オイルロード」と民主主義
